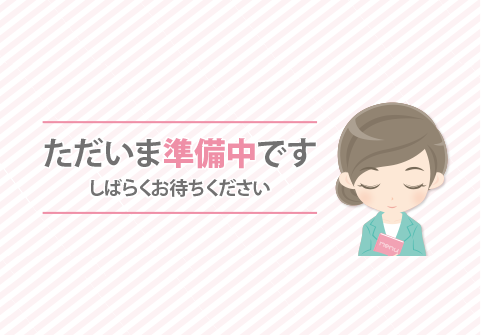働き始めてから臨床看護の勉強をしても、間に合いますか?
1年目看護師、病棟勤務、臨床看護の勉強を始めたい
看護師として働き始め、3か月の新人看護師です。看護学校での成績は中の下、実習もなんとかクリアーし国家試験にも合格できました。ただ正直なところ、真剣に勉強した記憶がありません。
患者さんの病名をみてもまったくわからず、何を注意して観察していけばいいのかわからないのはさすがにまずいと思い、仕事から帰った後勉強をしています。でも今から勉強しても間に合うのでしょうか。この先が不安です。
医療の進歩は早いですから、何でも知っているように見える先輩看護師も医者もでも常に勉強をしながら経験を積んでいます。
また座学と現場で必要な知識には違いがありますので「今から勉強しても」と悩む必要はないですよ。それにこれからも勉強をしながら経験を積んでいくのですから、決して遅いということはありません。
ただ先輩からの突っ込みが入ると「知識がないからわからない」とパニック状態になる新人看護師も多いです。そこで、新人看護師が知っておくと自信をもって業務ができやすい知識についてお伝えします。ぜひ参考にしてみてくださいね。
1. 解剖生理学をマスターしておこう
看護学校でも1年の時に習うことが多い解剖生理、まだ記憶しているでしょうか。内科・整形・外科・脳外ほかすべての科に共通するのが解剖生理です。
整形や外科病棟に配属されていれば骨折やオペが必要な患者さんが多くなりますので、解剖生理に触れる機会も多くなります。
ただ内科や他の科に配属されていると、さほど解剖生理の知識に必要性を感じないかもしれません。とはいえ、このような経験はないでしょうか。
・患者さんの導尿をする時、尿道口と膣の位置がわからなくなった
・急変による心臓マッサージの時、心臓の位置がわからなくなった
・血管がわかりにくい患者さんの採血や点滴で苦戦した
・筋肉注射をする時の、施注部位がわからなくなった
横で先輩が見ている時や苦手な患者さんに処置する時など緊張しますね。そこで先輩から「解剖生理わかっているよね?」とささやかれたら「ここで失敗したらどうしよう」「知識のない新人だと思われたくない」と頭の中はパニック状態になるかもしれません。
解剖生理の知識はあるのに、実際患者さんを目の前にすると混乱してしまうこともよくあります。先輩の前では、失敗は避けたい気持ちが強くなりがちなので「それくらい知っている」「それくらいできる」と思いこまず、もういちど解剖生理を復習しておくと慌てる回数も減ってきますよ。
2. 検査データの正常値を把握しておこう
検査データをみると、異常値がわかるようになっていますよね。でも異常値がでている原因までアセスメントすることはできるでしょうか。
すべてのデータを事細かに分析する必要はないですよ。ただなぜ異常がでているのか・考えられる原因はどこにあるのかなど、「なぜ?」という疑問をもつようにしてみるといいですよ。
検査データは覚えるというよりも、データからアセスメントできるようになることで疾患の理解も深まります。ただ自己判断でデータをもとに患者さんに指導をすることはやめておきましょう。
新人看護師の間は、ぜひ「この異常値がでているのはなぜ?」ということにポイントを置いて調べてくと知識が入りやすくなります。検査データハンドブックを、白衣のポケットに忍ばせておくのもおすすめです。
3. 心電図やモニターを理解できるようになろう
心電図は、検査技師さんが測定する職場も多いですよね。ただ夜間の入院や急変などで心電図測定を依頼された場合には、看護師が測定することもあります。先輩の手が離せない時、心電図を取るように指示された経験があるかもしれませんね。
また一度も測定したことがないという場合でも、この先機会があるかもしれません。ここでも解剖生理を役立たせ、どの部位に電極をセットするのかをイメージしておくと慌てずにすみます。特に急変時の場合正確なデータを取ることが重要になりますので、ぜひイメージトレーニングしてみてください。
また異常波形がわかるようにしておくと、知識が深まります。正常波形と合わせて異常波形で予測される原因まで理解できるようにしておくと、臨床で役立てることができますよ。
そしてモニター管理もできるようにしておくと、より安心です。夜勤でモニター管理の患者さんがいると、不安になりませんか?異常波形が早期発見できるようにしておくと、不安も軽減されますよ。
4. オペ後の観察ポイントを押さえておこう
先輩から「明日は○○さんのオペだから、術式を調べてきて」と言われた経験はないでしょうか。術式をと言われたのですから、先輩から質問されてもいいように予習してきますよね。
でも当日になって、先輩から一向に質問されないこともよくあります。「あれだけ必死に勉強してきたのに」という気持ちにもなりますが、先輩は新人看護師に言ったことを忘れていることもあります。
看護実習であれば、術式だけを調べてくればいいかもしれません。しかし新人とは言え看護師ですので、術式だけではなくオペ後の観察ポイントを押さえていきましょう。
共通する観察点は、疾患・年齢・性別などでも違いはあります。オペ直後から数日間、どこに観察ポイントを置いて観察すればいいのかまで事前学習しておくと、安心ですよ。
さいごに
4つの例をあげてお伝えしてきました。もしかすると「それくらいわかっている」「知っていて当然」と思うかもしれません。看護学校ではテストをクリアーするためまた国家試験に合格するために勉強をしていきますので、卒業して間もない間は記憶に残っていることも多いですね。
ただ座学で覚えて知識と、実際現場で患者さんを看護するために必要な知識にはズレが生じていることもあります。とっさの判断や緊張から一瞬で忘れてしまうこともよくありますので、現場で活かせる知識を身に付けていってくださいね。
「今から勉強しても間に合うだろうか」という気持ちになる必要はなく、これからも勉強を続けながら看護師としての知識を深めるための参考にしてみてくださいね。
看護師としてさらにスキルアップを目指すなら、転職エージェントに相談してみるのもおすすめです。医療業界に精通したコーディネーターが、あなたのキャリアプランを叶えるための方法をアドバイスしてくれますよ。ぜひお気軽に問い合わせてみてください。